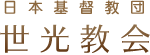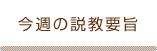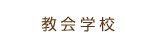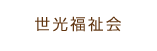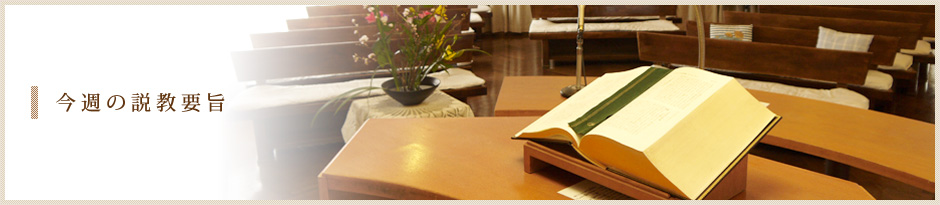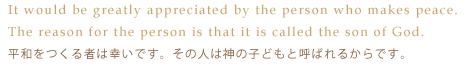2013年8月18日
■証し 林栄子姉(音声でお聞きください。)■説教「腰に帯をせよ」
榎本栄次 牧師
ヨブ記 40章 1-32節
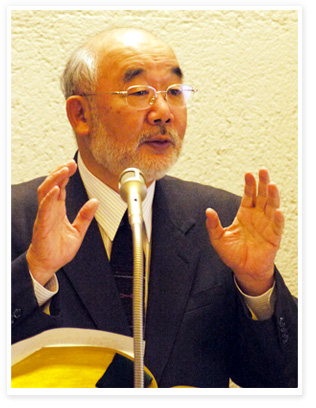
8月は6日、9日、15日過去の痛ましい戦争の反省に立つ平和を願う日が続きます。過ちを二度と繰り返さないように、深い祈りと実践が求められています。主イエスは「平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」(マタイ5:9)と言われました。今も世界の各地で戦火が止まず、爆弾の真下で多くの子どもやお年寄りが犠牲になっています。そこでは主イエスご自身が共に痛み、耐え、悲しんでおられます。互いに深い悔い改めをし、世界平和を祈り求めましょう。
嵐の中から神に語りかけられたヨブは、もう何も言うことはありません。「わたしは軽々しくものを申しました。どうしてあなたに反論などできましょう。わたしはこの口に手をおきます。ひと言語りましたが、もう主張いたしません」(4,5)とただ沈黙するばかりです。この沈黙は、完膚無きまで打ち砕かれたにも関わらず、喜びに満たされた沈黙です。ヨブはこれまで、神に反抗し、自分の思いをぶちまけていましたが、それは神への不信からではなく、神への真剣な問いかけであり、信じがたいが故の苦悶でした。今、主の答えによってすっかり納得できたのです。絶望ではなく喜びの沈黙です。
神はそのようなヨブに対して「男らしく腰に帯をせよ」と呼びかけています。打ちのめされているヨブにとって、「腰に帯をせよ」とはどういうことでしょうか。これまで自分の弱さや罪を認めようとせずに自分の強さと義にしがみついていたヨブですが、今はその必要がなくなりました。神により自分の弱さ、罪深さを知らされ、言葉をなくしているヨブこそ、「男らしく腰に帯をせよ」という言葉を受ける強さがありました。(注ヨシュア記1:9)
パスカルは人のことを「考える葦」と言いました。人は葦のように弱い存在である。しかし人は考えるから強いというのです。確かに、その強さで人は宇宙をも征服しようとしています。しかし、それは真の強さではありません。ここでも葦にすぎないことには変わりありません。
モーセの後継者であるヌンの子ヨシュアに対して主は「わたしは強く雄々しくあれとあれほど言ったではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神、主は共にいる」(ヨシュア記1:9)と言っています。弱く怯えるヨシュアが立つのは主が共にいますという現実に立つことでした。
またイザヤは「草は枯れ、花はしぼむが、わたしたちの神の言葉はとこしえに立つ」(イザヤ40:8)と預言しました。人の強さは、自分のうちにあるのではない。イザヤの結論は「主に望みをおく人は新たな力を得、鷲のように翼を張って上る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。」(イザヤ40:31)ここにあります。ヨブはこの新たな力を得たのです。それは主を信頼してその御心にしっかりと立つと言うことです。
近年の青年期の人たちに多く見られる傾向として、モラトリアム人間という心理状態が指摘されます。社会に出るのが怖くていつまでも、親がかりでいたいという心理です。外のことが分からないから怖いのです。松山教会員で東雲学園の前校長の妹尾先生はその心理を、内から外へしかものを見ない「インサイド・アウト」と言っています。パイロットはコックピットの窓からしか物を見ない。目の前の狭い視野しか見えません。ですから、「アウトサイド・イン」という管制塔からの指示がなければ、ニアミスや衝突事故が起きてしまいます。アイデンティティの確立が必要な時、どうしても大人になりきれない人が多くなってきている。それは外からの声を聞く機会が非常に少なくなってきているからであるというのです。
私どもは聖書によって自分の姿が照らし出され、私どもをそのまま許して下さる主の姿をしっかりと見つけてその後に従う時、安心してそのコースを行くことができます。自分が強くなるのではなく、神の御心による時こそ心の強さが得られるのです。そしてそこにこそ主の支配される平和が築かれるのです。真の平和もまた、神の臨在を仰ぎつつ、雄々しくつくられるものでしょう。