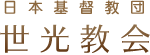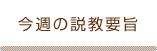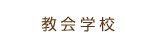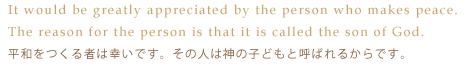2012年9月16日
「人は何者か」
榎本栄次 牧師
聖書 ヨブ記 6章 1-30節
人は土の塵からできたというのが、聖書の人間観です。すなわちそのルーツはまことにつまらないものであり、命のない形だけの物だというのです。しかしその土の塵に神の息(聖霊)が注がれ、生きた人間にされました。土の塵が意味があるのではなく、それに神の霊がかけられることにより、かけがえのない命が現れた。そこに人間の尊さがあるのです。土の塵が尊いのではない。神の息がかかった塵が尊いのです。ここに聖書の人間観が示されています。
ヨブは今、自分が土の塵のようになり、飢え渇き、絶望のどん底におかれています。豊かで栄えていた時には、人々は寄り集まりそこで憩い、神を賛美し、ヨブのことを褒め称えたものでした。人間としての存在を実感していました。しかし今はその面影は全くなくなり、枯れ果てた土塊のようになってしまいました。ヨブはそこで死なせてくれと神に願うのでした。ヨブの苦しみは人が耐えうる限度を超えたものでした。その苦しみを天秤に載せるなら、「海辺の砂よりも重いだろう」(3)と言い、この悲劇を神の仕業として「全能者の矢に射抜かれ、わたしの霊はその毒を吸う。神はわたしに対して脅迫の陣をしかれた」(4)と悪態をつくようになりました。
人がこのような苦しみにあっているとき、ただ黙して耐え続けることを誰が要求できるでしょうか。腹を空かした牛がうなるのを誰が止めることができるでしょうか。ヨブはその様な苦しみを吐露したのでした。その様子を見た友人たちは驚くのです。そして長々と説教を始めました。長老エリファズは、ヨブの過去を引き合いに出して現状の弱さを批判し、あるいは叱咤激励し、また神への信頼を奨励し、現状を教理的に分析し、将来への楽観的な希望を語って聴かせるのでした。しかしこの言葉は無駄であり的はずれであるだけではなく、ヨブをさらに苦しめ、痛みつけるものでした。
ヨブはこのような友人の的はずれな反応に戸惑い、失望します。教条的に説教するよりも「絶望している者にこそ、友は忠実であるべきだ」(14)と訴えます。ヨブはまた言います。「わたしの兄弟は流れのようにわたしを欺く」(15)と。「流れ」というのはパレスチナ地方に多いワディという谷川のことですが、雨季には短期間に多量の降雨があり洪水にもなりますが、乾季になると数ヶ月にわたり一滴の雨も降りません。荒れ野を旅する人が水を求めワディにたどり着いてみると一滴の水もなく失望してあわてふためくのです。慈しみを欠いた友人が、悩みの中で慰めを求める者に、苦しみと絶望しか与えないのでした。
われわれにとってよいものは隠されており、また、永遠なものであるからこそ、逆の相の下に隠されているのである。・・われわれの生は死の下に、われわれの愛は憎しみの下に、誉れは恥の下に、救いは滅びの下に、支配は追放の下に、天は陰府の下に、知恵は愚かさの下に、義は罪の下に、力は弱さの下に隠されている。・・・神は否定的な本質、善、知恵、義であって、われわれが肯定するすべてのものの反対の形でなければ、得ることも、達することもできない」(ルター著作集二)と言っています。
さて人は何者でしょうか。塵のような存在になった時、その存在の根拠はどこにあるのでしょうか。この塵を私たちは飾り立てて神の本質を表そうとしますが、そうすればするほどそれから離れます。また逆にその塵なるものをバカにして見過ごしてしまうのです。金銀で飾り立てたとしても、それでは人になれません。所詮塵にかえるしかないのです。
私たちが何かしようとした時、自分の無力に気づき、砂を噛むような空しさや、絶望に支配されます。しかしそこに神様が隠れておられる、その神に出会い、力にふれるのです。だからどんな小さなこと、恥ずかしいことも無視できない。むしろその小さいことに徹し、注意するのです。そこで苦しむ友を支えるのです。そこで人としての本質に出会うのです。