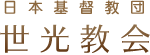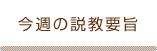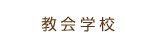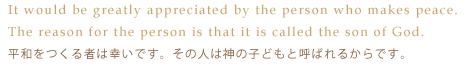2011年3月20日
「キリストの土台」
榎本栄次 牧師
聖書 コリントの信徒への手紙Ⅰ 3章 10-17節
何を土台に据えるかが問われます。平穏なときは何も変わりませんが、いざ何か起きたときに、その人は何を基本にしているかが問われ、本質が暴かれるでしょう。その時になって慌てないようにすることを終末論的生き方といいます。週末の時に目を向け、そこから今の自分を計り決めるのです。東日本大地震に遭い、あらためて考えさせられています。「何が来ても大丈夫」「どんなに大きな地震が起こっても、どんなに大きな津波が来てもビクともしない」と豪語していたはずの福島原発でしたが、今回の大地震の前には全く無力であることを明らかにしています。それでもまだ大丈夫と言っている人がいます。それと同じように、私たちも「自分は大丈夫」「どんな試練にも耐えてみせる」と強がっていても、いったん何かが起きると、いかに無力であるかを知らされます。不安感をあおるつもりはありませんが、これは相当深刻に受け止めた方がいいのではないかと思います。
使徒パウロは、「神からいただいた恵みによって、熟練した建築士のように土台を据えました」(10)と言っています。それは「イエス・キリストという既に据えられた土台」(11)の上に、私たちが家を建てるということです。その家が何でできているかが問われます。金、銀、宝石、木、草、わらで家を建てます。パウロの場合、「熟練した建築士のように」コリントの教会を建てたのでした。
私たちもまたそれぞれにキリストを土台とした家を建てるのです。かつて北海道で開拓伝道を始めようとした頃、会堂はおろか一坪の土地もありませんでした。その時に願ったことは、共に礼拝できる場所が必要だ、わらで囲ったような所でもいい礼拝するところがほしい、と願ったものでした。むしろで囲った礼拝堂を想像して、そこにロマンさえ感じていました。当時韓国の貧民窟で礼拝している「ガリラヤ教会」(新教出版)が紹介され大きな刺激を受けました。そこにいる人たちの信仰共同体としてのパワーに魅せられて、自分たちもそのようでありたいと願ったのでした。そうしてできたのが札幌北部教会です。
金であるか、わらかは目に見える材質ではなく、信仰の質でしょう。自分たちの教会は巨財を積んだ金でできた教会だ、というのもあります。すごい田舎で大きな会堂があるけれども、数人の礼拝参加者というのもあります。わらのように焼かれてなくなってしまいそうな教会もあります。そういうところに、不動の強い信仰が根付いていることもあるでしょう。
いずれにしても、いざという時には耐えられず、焼け崩れてしまいます。その時何を土台にしているかが問われるのです。「その人は、火の中をくぐり抜けて来た者のように、救われる」(15)という言葉は慰めに満ちています。教会を建てるために、宣教活動を進めるために、一人でもキリストの救いに導き入れるために、走り回り、多くの人から喜ばれるよりも恨まれ、邪魔され迫害を受ける姿は、まさに「火の中をくぐり抜けて来た者のようで」あったことでしょう。しかし救いの現実はそこにしっかりと根付いており、その人の顔は希望に輝いています。この言葉にどれだけ励まされたことでしょう。顔はすすけて髪は焼けこげてちりぢり、服は破れてぼろぼろ、情けない格好なのですが、それらが勲章のように輝くのです。自分は、焼けない、嵐にも津波にも負けない強さがあると豪語していても限界があるでしょう。私たちはその時、大きな損失を被る建物です。神御自身がその裁きを起こされるのでしょう。その対象はほかならない教会です。パウロはまた、「あなたがたは神の神殿なのです」と勧めます。わらのようにみすぼらしい建物であってもそれはキリストを土台にしているから「神殿」です。私たちはその上に家を建て、神の神殿を建てるのです。